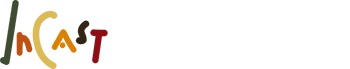InCASTを立ち上げて4回目の開催となる今回、InCAST Tokyo 22と題して初めてポーランドのメンバーがチェコの作家と共に来日しました。交流の母体となるシュチェチンのアートアカデミーのメンバーの中には既に来日経験者もいますが、今までのInCASTはポーランドと日本それぞれの会場にデータやオンラインで参加するという方式だったのでスクリーン上で出会っていた本人たちと共に日常的な時間を共有する事ができたのは大きな成果でした。
今回のアップタウン・高円寺ギャラリーにおいてチェコ・オストラヴァ大学のトマス・コウデラ教授による展覧会場の空間構成は秀逸で作品やメディアの特質をとらえたメリハリの効いた会場になりました。特にヨーロッパ側からプリントや動画作品の参加者が30名以上になったことは今までにない成果でしょう。もちろん日本側も都内に限らず京都や佐賀などから映像や絵画などが集まりました。
また、アップタウンの地下では国際会議の会場を設置し、まさに6〜70年代のアンダーグラウンド、カウンターカルチャーを彷彿とさせる知的な発表空間でした。アンドレアス・グスコス(シュチェチン・アートアカデミー)と犬塚潤一郎(実践女子大学)両教授による基調講演もAIとアートの関係やプラトニズムとフラクタルデザインの関係など同時代的なテーマで刺激的なものになりました。
言葉によるカンファレンス全体を挟む構成として初めと終わりに身体表現を取り入れました。はじまりは山田有浩による20分ほどの舞踏で削ぎ落とされた肉体が狭い椅子の上で危ういバランスを保ちながらも最後に落下する様はあたかも不可視のルールに拘束された現代人を風刺しているようで、落下すると同時に世界に色が蘇るような解放感は観客もまた体験を共有していました。
また、カンファレンスの終わりは柴崎正道の「ダンスとメディアが併置されたパフォーマンス」でした。ギャラリー内部で生々しい息遣いの肉体とリアルタイムに拡大された体の部分映像が鑑賞者に初めての視聴覚体験をもたらしました。
本編のカンファレンス自体もそれぞれ中身の濃い研究成果が伺えるものでポーランドはもとよりメキシコやスイスからもエントリーがありました。
前回までのデータを通した交流展覧会やカンファレンスも現実の時空間で共に開催することでInCASTがスクリーンの中だけではなくなりよりリアリティを持った出来事になりました。